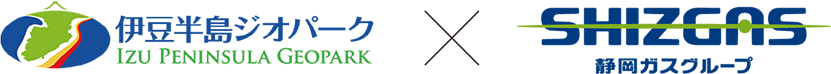Archiveアーカイブ
2025年10月18日(土)
環境
「狩野川放水路へ行ってみよう」
当日レポート

- 場所
- 狩野川資料館・狩野川放水路
秋晴れの下、会場となった狩野川資料館にはたくさんの参加者が集まりました。最初に沼津河川国道事務所の宮城さんから、ビデオ上映を交えながら放水路の成り立ちを伺いました。伊豆半島最大の流域をもつ狩野川は、かつて頻繁に氾濫を起こしており、被害を減らすために放水路建設が始まりました。しかし完成前の昭和33年、狩野川台風が直撃し、死者・行方不明者853名という未曽有の被害をもたらしました。映像では当時を知る方々の証言もあり、その衝撃の大きさを改めて実感しました。
その後、ヘルメットを着けて放水路見学へ。最初に水色の鉄橋から本流と放水路をつなぐ水門を見学。通常は閉じていますが、水位が上がると開き、毎秒2000立方メートル、つまりたった1秒で25mプール4杯分の水を逃がすことが出来るのです。河原では、セイタカアワダチソウの黄色い花やススキの銀色の穂が風にたなびく中、放水路のトンネルへと続く道を歩きます。ふだんは立ち入り禁止のエリアですが、この日は特別。放水路へ向かう坂道を下る途中、ふと見上げると河岸に目盛りがついています。これまでに発生した台風や大水の名前と、その際に水が達した高さが記されています。目の前に広がる広大な放水路と見比べながら、どれだけの水量だった想像し、自然の力の壮大さに思いを巡らせました。
目の前には巨大なトンネルの入り口が3つ。そのうちのひとつの中へ入りました。 高さ11メートル、長さ850メートルの巨大なトンネルで、構造物の大きさに圧倒されます。奥の方には小さく出口が光っていました。その先にさらにもうひとつトンネルがあり、海へ注ぐようになっているのだそうです。途中、参加されたお子さんが、水たまりに小さな生き物を見つけました。「この虫はなーに?」と先生に聞きます。そうです。今日はもうひとり、生きもの博士がツアーに同行しているのです。静岡県の環境保護調査委員会の川嶋先生が、「トンボの幼虫だよ」と教えてくれました。
トンネル見学が終わった後は、川嶋先生から狩野川に棲む魚のお話。天城を源に流れる狩野川の特徴や、流域ごとに異なる魚たちの姿、同じ魚種でも川によって違いが出るという自然の不思議など、興味深いお話をお聞きすることができました。魚が大好き!という先生、時間も忘れてお話しする情熱は参加者の皆さんにしっかり伝わったようで、参加者からは「楽しかった」「勉強になった」との声が多く聞かれました。
イベントの最後には、狩野川の恵みを味わう鮎のお弁当をお持ち帰りいただきました。焼き鮎の混ぜご飯や甘露煮など、川の恵みがぎっしり詰まった美味しい一折です。
今回のイベントを通じて、時には脅威として、また命を育む存在としての「川」と、私たちの暮らしとのつながりを改めて感じていただけたのではないでしょうか。

狩野川の本流から分岐する場所で水門の説明を受けます。

これまでの台風や大水の記録が記された目盛り。

奥の方に小さく出口が見えます。

構造物の大きさに圧倒。

足元の水たまりに、小さな生き物を発見。

説明に熱心に耳を傾ける参加者。

これだけの広さを埋め尽くす水の量っていったい…。

黄色や銀の穂がたなびく秋晴れの中を歩きました。