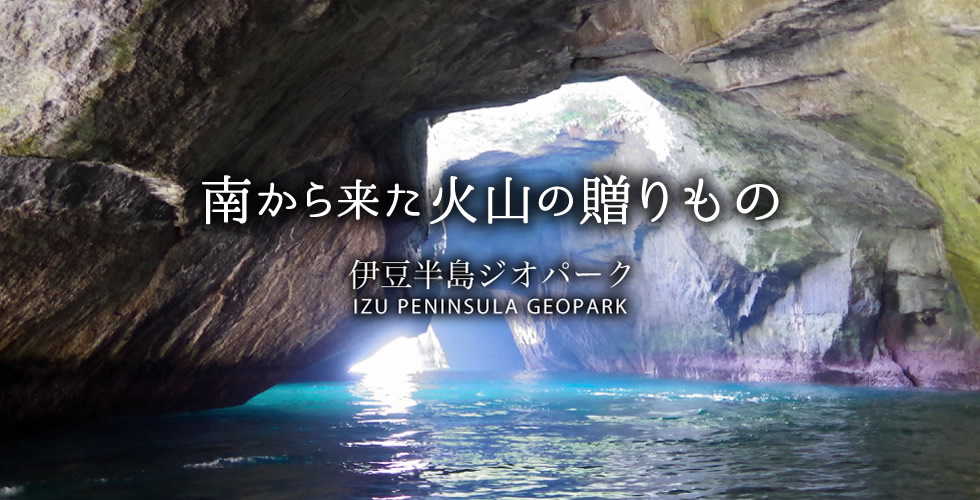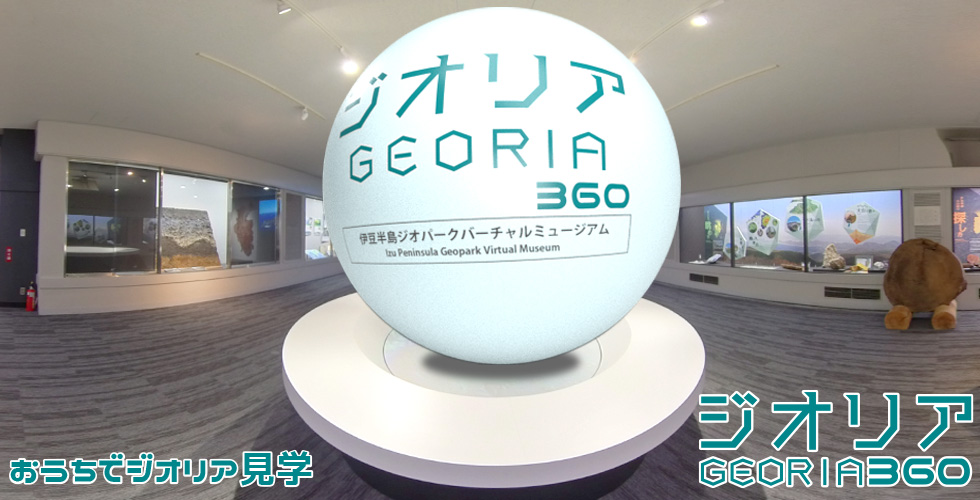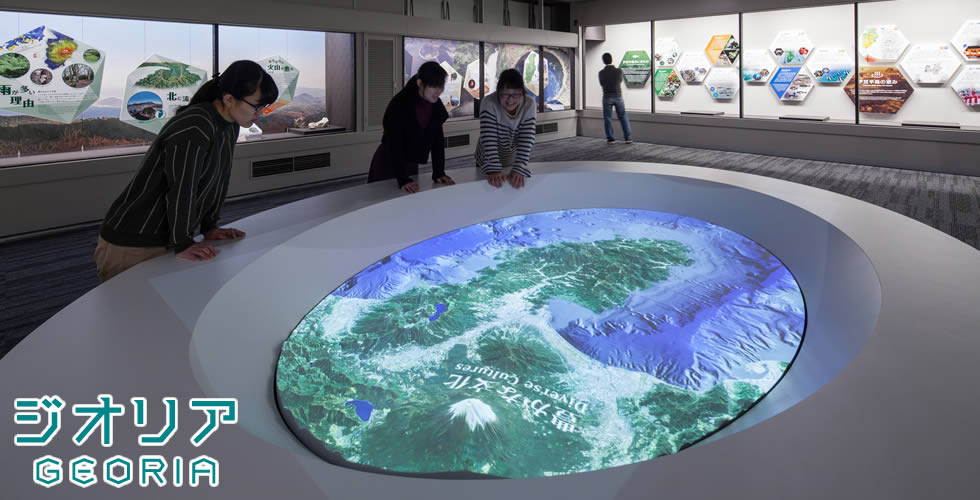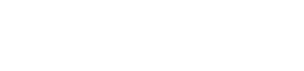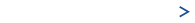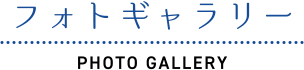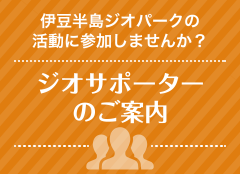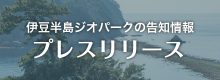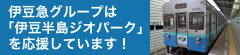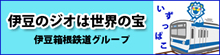- カテゴリーから探す
- 成り立ちから探す
- 地形から探す
- 地域から探す

-
2024年 4月 11日
海藻おしばづくりワークショップ
今年のこどもの日は、伊豆の海のことを教えてもらいながら、色々な種類の海藻を材料に、自分だけの作品を作...
-
2024年 4月 9日
【延期】ジオカフェ「ツナグ 陸-海 ~漁師の森づくり~」
2022年7月より、伊豆急行の路線を走っているジオトレイン「ツナグデンシャ」では各車両で、「世界と伊...
-
2023年 11月 7日
【終了しました】トークジオカフェ「おんせんはたいへん」in河津温泉郷
今年も「おんせんはたいへん」を開催します!今回は、川端康成の小説「伊豆の踊子」の舞台ともなった温泉場...
-
2023年 10月 17日
【終了しました】11月5日伊豆半島の写真絵本を作ろうワークショップ
11月はジオリアで写真絵本を作りましょう。当日は講師として、写真家であり写真絵本作家でもある小寺卓矢...